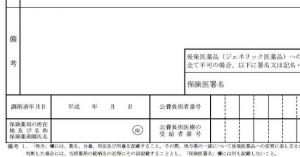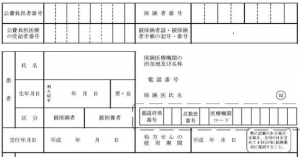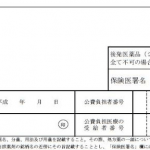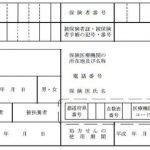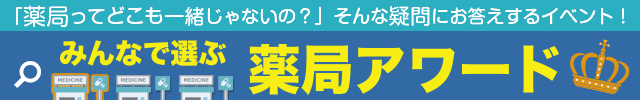- HOME >
- 薬剤師のお仕事マニュアル >
- 医療事故・ヒヤリハット >
- 医療事故を減らすためのKYT(危険予知トレーニング)とは?
医療事故を減らすためのKYT(危険予知トレーニング)とは?
うっかりミスなど人間の特性が表れないシステムが重要
KYTとは、危険(Kiken)+予知(Yochi)+トレーニング(Training)のこと。
もともとは建築現場で使われていた言葉で、作業の中に潜む危険を話し合い、予知と対策を行う訓練です。
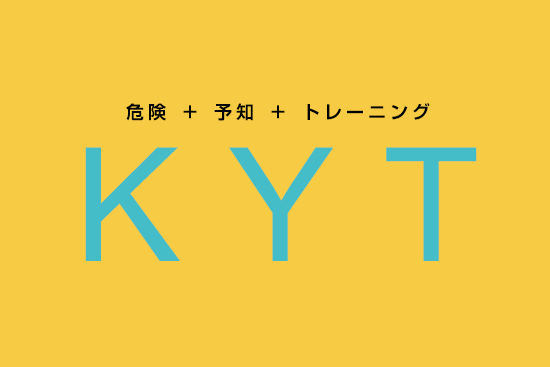
近年、医療従事者のKYTに注目が集まっているのは、医療事故から訴訟になるケースが増えている背景から、医療事故を減らすための対策として有効だと考えられたからです。
「人間はミスを犯す特性がある」
これがKYTの大前提です。ミスをしない人間は皆無に等しく、人間には「不注意(うっかり、ぼんやり)」「錯誤(思い込み)」「省略行為(慣れ、横着)」「焦り(先を急ぐ、パニック)」などの特性があります。
KYT(危険予知トレーニング)に期待される効果
KYTは、これらの特性を変えようとするのではなく、これらの特性が表れないシステムが重要だと考えられ、KYTを行うことで以下のような効果が期待できます。
- 危険への感受性を高める
- 危険に対する集中力を高める
- 問題解決力・意欲を高める
- チームワークの強化
- 安全意識の高い職場となる
現状把握・原因追究・対策立案・目標設定をするイラストKYT
KYTには、イラストから危険を予測し対策を立てる「イラストKYT」、指でさして声を出しエラーを減らす「指差呼称」、職員の健康状態を確認し問いかける「健康確認」の3種類があります。
イラストKYTでは、イラストの中に含まれる危険を予知することで、普段は気づかなかった危険を認識することができます。
たとえば、ベッドに寝ている患者さんに点滴をする看護師のイラストがあり、そこに潜んでいる危険を話し合い(現状把握)、危険のポイントを見極め(原因追究)、対策立案、目標設定をします。
- 現状把握
- 点滴台が固定されてなく、滑車がついているため台が倒れる可能性がある。
- 原因追究
- 点滴台が固定されてなく滑車がついているため、動いたり倒れてしまったりラインが外れてしまう。
- 対策立案
- 点滴台を床面に固定してから点滴を行う。
- 目標設定
- 滑車がついていない器具へ変え、点滴ルートの点検を徹底し、「固定よし!」と指差呼称する。
職員同士のコミュニケーションにもなる健康確認
指差呼称は駅員さんなどが行っているKYTのひとつで、認識した対象に対して「眼」「耳(声)」「手」で確認することで、作業を誤る確率は6分の1に減ると言われています。これは、薬剤師にとってもヒヤリハットを防ぐのにとても有効です。
健康確認は、「姿勢」「動作」「眼」「表情」「会話」などをとおし、職員同士で健康状態を把握することで、ヒューマンエラーや災害を防ぐことができます。
また、「目が赤いけど大丈夫?」「昨日遅かったみたいだけど大丈夫?」などと互いに声をかけあい健康確認を行うことで、職員同士のコミュニケーションにもつながります。
「人間はミスを犯す」とうい特性を大前提としたKYT。1日も早くすべての医療現場で導入されることを願います。
-
 働き方が変わる キャリア面談が好評正社員もしくはパート・アルバイトなど、腰を落ち着けて働きたい人で、業種未経験、新卒で経験が浅いなどの理由から転職に不安がある人にオススメ。 書類の添削や面接、条件交渉など、転職活動に関する様々なサポートが受けられる。
働き方が変わる キャリア面談が好評正社員もしくはパート・アルバイトなど、腰を落ち着けて働きたい人で、業種未経験、新卒で経験が浅いなどの理由から転職に不安がある人にオススメ。 書類の添削や面接、条件交渉など、転職活動に関する様々なサポートが受けられる。 -
 好条件の薬剤師求人が豊富公開求人情報は47,000件以上(2023年9月29日時点)と豊富。派遣求人のなかには時給3000円以上の求人も。ブランクがある薬剤師でも、グループ会社 日本調剤の教育ノウハウを生かしたスキルアップ・キャリアアップ支援サービスが充実しているので気軽に転職活動を始められる。
好条件の薬剤師求人が豊富公開求人情報は47,000件以上(2023年9月29日時点)と豊富。派遣求人のなかには時給3000円以上の求人も。ブランクがある薬剤師でも、グループ会社 日本調剤の教育ノウハウを生かしたスキルアップ・キャリアアップ支援サービスが充実しているので気軽に転職活動を始められる。 -
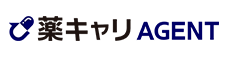 薬剤師登録数No.1 *年収は高め、かつ職場環境や勤務条件も妥協したくないというかたにオススメ。 日本最大級の医師サイトm3.comでお馴染みのエムスリーグループの薬剤師向けサービスでより多くの求人案件を吟味し、自分に合った求人を比較検討できる。*エムスリーキャリア調べ
薬剤師登録数No.1 *年収は高め、かつ職場環境や勤務条件も妥協したくないというかたにオススメ。 日本最大級の医師サイトm3.comでお馴染みのエムスリーグループの薬剤師向けサービスでより多くの求人案件を吟味し、自分に合った求人を比較検討できる。*エムスリーキャリア調べ
薬剤師の転職サイトについて、さらに詳しく比較したいかたは「薬剤師が選ぶ人気転職サイトBEST5」もご覧ください。
カテゴリ一覧
- 医薬品について
- 業務について
- 経営・管理について